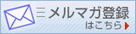振る舞いの特徴
「最上志向」の回でも少し触れましたが、「回復志向」は物事が本来あるべき状態から離れてしまったものを元の状態に戻す思考です。何事に対しても、何かしらの問題を見つけると、それを解決したいという強い願いが生まれ、実際に解決に向けて動き出します。そもそも、問題に気づきやすいという特性も持っています。 「回復志向」の人は、問題が解決されたという成果が得られるまで必要なことを実行します。「最上志向」と比較すると、「最上志向」は際限なく改善を目指すのに対し、「回復志向」は本来あるべき状態に戻すことを目的とし、一定の到達点があります。すなわち、問題が解決された状態や壊れたものが直った状態がその到達点です。 「回復志向」の場合、本来の状態に戻すという目的が達成された時点で、そのことに対する興味を失います。そして、次の問題に目を向け、解決に向けて動くというサイクルになります。 「回復志向」が自分自身や他人に向いた場合、その人の足りないところに目を向けることになります。自分の欠点や弱点に目を向けがちになり、他人に対しても自分に対しても、「直す」という感覚がここでも出てきます。 その意味で、「最上志向」の場合、自分の強みや良さを指摘される方が響くのに対し、「回復志向」上位の人の場合は、改善すべき点も指摘してもらうと、自分が何をすべきかが明確になり、ありがたく感じると思います。根源的な欲求、動機づけ
「回復志向」の根源的な欲求は、物事を本来のあるべき状態に戻したい、すなわち文字通り回復させたいということです。そして実際に、本来の状態を取り戻したという成果を得ることにあります。この欲求が、「回復志向」固有の思考、感情、行動のパターンを引き出します。強みとして活かせている状態
何と言っても、問題解決能力に長けているところが最大の強みです。「回復志向」上位の人は、問題を見つける能力にも長けています。なぜなら、根源的な欲求が本来の状態に戻したい、すなわち問題がある状態をそうでない状態に戻したいという欲求が根底にあるからです。そして、一旦見つけた問題に対しては、おざなりな対応を取ることなく、そこにある根本的な原因を取り除こうとしますし、実行力の資質でもあるので、実際に解決に向けて行動、実行が伴います。 こうして他の人が見過ごしそうな問題も目ざとく見出し、細かな改善を繰り返し、プロジェクトを本来あるべき軌道にしっかり乗せていくことができるのが「回復志向」上位の人だと思います。 対人においては、特定の人が何かしら問題を抱えている場合、それを解決してあげたいという気持ちも出てくると思います。そのため、その人の抱える問題の解決に向けて、自分が有益な情報を持っている場合は、それを喜んで提供し、アドバイスしてあげるでしょう。「回復志向」上位の人は、物事でも人でも何かしら問題があることを当たり前だと捉えています。だからこそ、何かしらできないことがある人に対しても「待てる」感覚があるのではないでしょうか。 特に「成長促進」を併せて上位に持つ人だと、その感覚がより強くなります。すなわち、人材育成においては、何かしらできないことがある人も辛抱強く見守り、改善に向けて共に取り組む姿勢になるでしょう。妨げになってしまっている状態
基本的な欲求が問題解決にあるため、どうしても問題を探すことに意識が向きがちです。どんな資質にも共通していることですが、視野が狭くなってしまうと手段が目的化してしまいがちです。すなわち、プロジェクトを軌道に乗せて成果を出すことが本来の目的であるべきなのに、さほど重要ではない問題に意識を持っていかれがちです。 問題に目を向けがちだという自分の思考のクセを自覚し、メリハリをつけた使い方をすることが必要です。細かな問題が目につくかもしれませんが、それが今解決すべきものなのか、少し引いて見る、すなわち俯瞰して見ることが求められます。対人においては、どうしても直すべきところに目が向きがちなので、そういうポイントを他者に対してフィードバックしがちです。そういうところが人によってはネガティブに受け取られることもあるかもしれません。特に相手が「最上志向」や「ポジティブ」を上位に持つ人だと、そのように感じやすいです。 改善ポイントを指摘すること自体は悪いことではありませんが、どうしても指摘したい場合は、「あなたにより良くなって欲しいから改善して欲しいことを伝えます」というような伝え方をすると、相手も受け取りやすくなります。そして、問題解決欲求が人に向いた場合、ややおせっかいに感じられることもあるかもしれません。人は本来、自分の問題は自分で解決できる力を持っており、その権利もあることを思い出し、過度に世話を焼かないことも必要です。 その意味でも、人との関わりにおいてお互い率直に物が言い合える関係性を築いておくことが大事です。「回復志向」に限ったことではありませんが。効果的に活かす方法
これまで述べてきたように、「回復志向」の強みは、その高い問題解決能力にあります。この資質は、問題を発見する能力に長けており、見つけた問題を解決に導く能力も秀でています。どのような場面でこの能力を最も効果的に活かすかを考えることが重要です。この点では、自分がどの分野に特に興味を持ちやすいか、またどの種類の問題に取り組むときに最もモチベーションが高まるかを自覚することも大切です。 例えば、「回復志向」とともに人間関係の構築能力が比較的上位の場合、人間関係に関する問題に意識が向きやすいでしょう。「調和性」が高い場合、チーム内で意見が対立していると、その対立を解消したいと感じるでしょう。「共感性」が高い場合、周囲の人々が抱える問題に寄り添い、その問題を解決しようという気持ちが芽生えるはずです。一方で、実行力や戦略的思考が強い場合には、プロジェクトのトラブルシューティングや技術的な問題への対処に意欲がわくことでしょう。また、仕事のプロセス改善が求められた際には、「回復志向」を活かして問題の根本を探求することが得意分野として挙げられます。 自分の得意分野を意識しながら、それを活かす適切な場面を選んでいくことが重要です。これは、ある意味で役割分担や自分の出番のタイミングを見極めることにもつながります。例えば「最上志向」上位の人のように、人によっては問題点に目を向けづらいこともあります。そのため、見逃せない問題が生じた際にそれを指摘し、チーム全体の注意をその問題に向けさせる役割を「回復志向」が果たすことがあります。 タイミングを計ることは、「回復志向」を前面に出していくのか、あるいは抑えるかのメリハリをつけることにも関連します。手段が目的化してしまわないように、物事の全体を俯瞰し、必要なタイミングで介入することが大事です。問題が明らかになって放置するのは心苦しいかもしれませんが、プロジェクト全体の最適化を考慮し、敢えて手をつけないという判断も時には必要です。 さらに、「回復志向」上位の人は問題が存在することを自然なことと受け止め、緊急のトラブルが発生しても過度に慌てることなく対処できるのではないでしょうか。特に「適応性」や「ポジティブ」が併せて高い場合、「起こったことは仕方ない」と受け止めたり、「何とかなるだろう」と前向きに考えることができます。このような場面で「回復志向」上位の人は、周囲から見て頼もしい存在として映るでしょう。対比される資質
統計的に見て、順位が離れやすいのは「最上志向」です。ただし、二つともが上位の方は必ず存在するので、真逆の資質同士というわけでは決してありません。ある意味妥協なく改善を目指すというところは、二つの資質に共通するところでもあります。 異なる点は、改善するポイントをどこに置くか、そして改善した先に到達点があるか否かです。「回復志向」の場合は、問題のあるところ、出来ていないところ、不足のあるところに目を向ける傾向が強く表れます。そして、それらを本来の状態に戻すべく行動が伴います。すなわち、本来あるべき状態に戻ったところが到達点となります。 一方、「最上志向」は、既に出来ているところに目を向け、それをさらに改善させたいとの欲求を持ちます。既に出来ていることをさらに良くしたいという思考なので、そこには到達点が存在しないことになります。 こうして見ていくと、それぞれの視点がそれぞれに大事なものであることに気づけると思います。例えば、それが物作りであったとすると、製造過程に問題があれば直ちに解決しなければなりませんし、ひとたび出来上がった製品も、顧客ニーズに合わせて際限なく改善を続けていく必要もあると思います。 思考パターンの違いは役割の違いでもあります。順位が離れやすい資質同士だからこそ、お互いがお互いを尊重し合い、お互いの役割を最大限果たすことができれば、どんなことでもより良いものになっていくということだと思います。他の資質との組み合わせ
他の資質との組み合わせにおいても当然ながら「回復志向」固有の思考が反映されます。既出ですが、「共感性」との組み合わせだと、相手の心の痛みを取り除いてあげたいとの気持ちになりやすいので、何か困りごとを抱えている人を放っておけない感じになります。 「回復志向」の“修復したい”という欲求が「調和性」との組み合わせだと、対立を解消させたいという欲求に基づく行動につながります。トラブルや問題はあるのが当たり前との感覚と共に、「適応性」が上位だと、予期しなかった緊急のトラブル時にも過度に慌てることなく(場合によってはむしろワクワクしながら)対処にあたると思います。 問題解決という意味では、「分析思考」や「原点思考」が加わると、根本にある原因をしっかり押さえた上で解決に導くという感じになります。出来ないことがあって当たり前との思考と「成長促進」が結びつくと、自分が放っておいても出来てしまう優秀な人よりは、むしろ出来ないことがある人の方に惹かれ、出来るようになるまで辛抱強く見守る感じになると思います。 様々な資質との組み合わせにおいても、「回復志向」の持つ本来あるべき状態にないものを本来の状態に戻したいという思考が反映されたものとなります。ここでも、そういう思考ゆえの強みを活かしつつ、何かの妨げになるほどむやみに使い過ぎないよう、メリハリをつけていくことが大切です。上記はギャラップに承認されたものではなく、ギャラップの認可も推薦も受けていません。クリフトンストレングス®(ストレングスファインダー®)に関する意見、見解、解釈は、株式会社ハート・ラボ・ジャパン代表 知識茂雄だけの考えです。
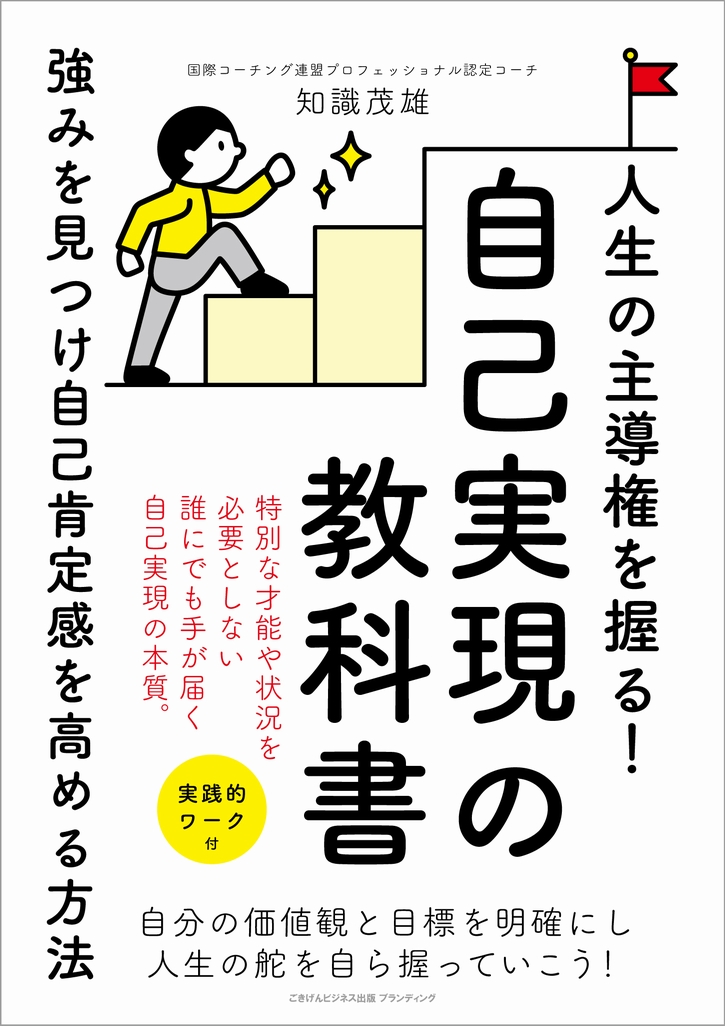
ストレングスファインダー®徹底活用ガイド
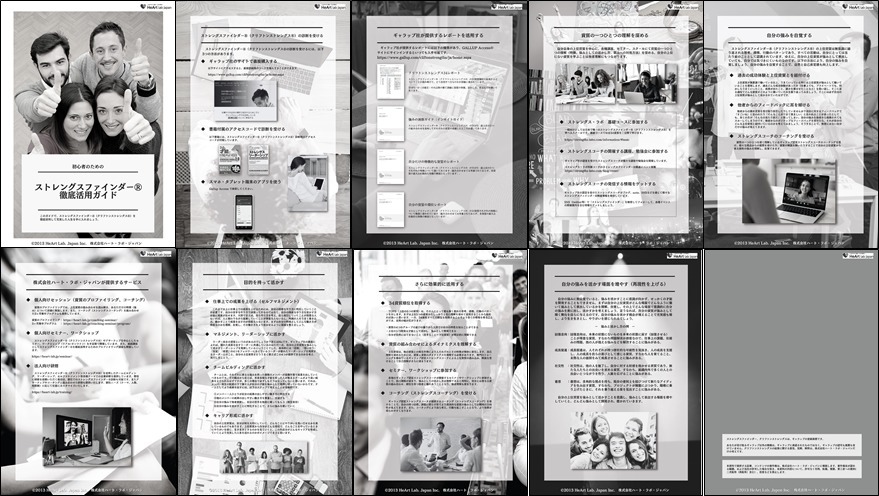 簡単なアンケート(選択式)にお答えいただき、メールアドレスをご登録いただくと上のストレングスファインダー®徹底活用ガイドをプレゼントいたします。お申し込みは、上の画像をクリックしてください。
簡単なアンケート(選択式)にお答えいただき、メールアドレスをご登録いただくと上のストレングスファインダー®徹底活用ガイドをプレゼントいたします。お申し込みは、上の画像をクリックしてください。
無料メルマガ「才能を活かして自分らしく楽に生きる方法」
思考を緩め、人間関係を改善し、自分らしく楽に生きる方法を、ほぼ毎日お届けしています。
メルマガ読者限定の特典も提供しています!