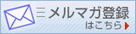クリフトンストレングス®(ストレングスファインダー®)の結果は環境に左右される?
ご質問を頂きました。メルマガをいつも楽しみにしております。 心理学に詳しい方から、ストレングスファインダー®の結果は環境の影響を受けないのか?という質問を受けました。 「心理学の大前提として行動=f(個人,環境)がある」とのことでした。 そのため、ストレングスファインダー®を受験した時期や環境から結果が変わるのではないか?と。 ストレングスファインダー®の資質は、環境に左右されない、生まれ持ってのものだと考えていますが、どうでしょうか。 いつかブログで取り上げていただきたいです。ご質問ありがとうございます。 まず最初にお断りから。 この先で書くことはあくまで私の個人的見解であり、ギャラップの公式見解ではありません。 また当方心理学に精通しているわけではありませんので心理学との関連については言及いたしません。 以降回答ですが、たぶんむちゃくちゃ長くなるのでお時間のあるときに読んでください。 クリフトンストレングス®で言うところの資質、すなわち才能のかたまりは「無意識に繰り返される思考、感情、行動のパターン」と定義されています。 すなわちこの意味での資質が(資質の順位が)環境の影響を受けて変わり得るかと言うのが問いになると思います。 結論から言うと(あくまで私の個人的見解として)多少は変わることがあり得ると思っています。 まず、クリフトンストレングス®で言うところの資質がどのように形成されるのかを考えると、遺伝的な要素とそうでないものと両方の要因があると思っています。 特に影響が大きいのは幼少期における親を中心とした周りの大人との関わりです。 シンプルに言うと、幼少期の子どもは大人に助けてもらわないと生きていけないわけで、その意味での自分なりの生存戦略を取っているはずです。 すなわち、いかにして親に構ってもらえるようにするかということ。 ここは恐らくベースとなる遺伝的特性も絡んでくるのでいろいろ複雑なのだと思いますが、極端な例で言えば親の顔色を伺いながら言うことを聞き良い子でいるとの選択をする場合もあれば、わがままさを発揮することで親の注意を引こうとする場合もあるでしょう。 私の場合で言うと(あくまで推測ですが)「最上志向」「調和性」「責任感」あたりの上位資質を見ると、優秀で聞き分けの良い子を目指してきたのだと思います。 「自我」も上位なのは、自分とは違い社交的な姉へのコンプレックスから別の才能を発揮することで認められたいとの欲求の表れなのでは?とも思っています。 いずれにしても資質というのは先天的、後天的両方の要因が影響しているものと私は考えています。 その前提で考えるならば、環境の影響で資質順位が“多少”変わることがあっても不思議ではないと思っています。 “多少”と書いたのは、資質順位が大幅に入れ替わるのはその人が全く違う人になってしまうことを意味するのでそこまで大きな変化は起こり得ないだろうと思うからです。 例えば私のように社交的でない人間がどんなに努力したところで「社交性」がTOP5に上がってくることはまずあり得ないと思っています。 少なくとも私くらいの年齢においては。 逆に言えば、いわゆる上位資質と下位資質が逆転するような順位変動はまず起こらないとしても比較的上位の資質の中での順位が入れ替わるというのは十分起こり得ると思っています。 例えば、仕事での与えられた役割が変わったときなどです。 具体的な例を出すと、病棟勤務の看護師さんと救急外来勤務の看護師さんでは同じ職業であっても求められるものが違ってくると思います。 救急外来勤務の方がより臨機応変さを求められるのではないかと思います。 どちらが大変とかいうことではなく求められる対応の違いです。 上記例において、病棟勤務から救急外来に移った方がたまたま「適応性」とか「アレンジ」がそこそこ上位だったとすると、救急外来に移ることでそれらの才能を活かす機会が増える、すなわち才能が磨かれていくことでそれらの才能(資質)がより上位に上がっていくということは考えられると思うのです。 とは言え、資質とは“無意識に”繰り返されるものなので資質順位の変動として表れるまでには相応の期間が必要なのだと思います。 ここまでの結論(私見)としては大きな環境の変化によりより必要とされる才能が変化しそれらの才能が磨かれて順位が上がり、逆にさほど必要とされなくなった才能(資質)の順位は下がっていくことはあり得る、ただし上位資質と下位資質が入れ替わるほどの大きな変動は考えづらいです。 ただここで再診断の際の診断の精度についても考えておく必要があります。 どんな人でも最初の診断の際はクリフトンストレングス®の資質の一つひとつにつき知識はないまま受けているはずです。 すなわちそこに先入観が入る余地はないはずです。 しかしながら特にこのメルマガの読者のようにある程度クリフトンストレングス®について学んでいると、診断を受けながら設問を読んでいて「この設問は“あの”資質のことを言っているのかな?」的に浮かんでしまうと思います。 すると、「本当はこういうのが欲しいけど自分にはないもんなぁ」とか、「この資質が上位だから困ったことが起こるんだよなぁ」とかの考えが浮かんでしまうことも考えられます。 こんな感じになってしまうと、もはや最初に受けたときとはまったく心理状態が異なるので診断の精度は落ちる(本来は上位にあるものが必要以上に下がったり、その逆が起こったり)ことが十分にあり得るのだと思っています。 上では上位資質と下位資質が入れ替わるような大きな変化は起こらないと書きましたが、こういう要因も加味すると何でもそうですが例外は起こり得ると言わざるを得ません。 そもそも血液検査のようにまったく客観的な検査ではなく、答えているのは自分であり自分の主観なので、そういう意味でもクリフトンストレングス®のような診断ツールに100%の“正しさ”を求めるのは無理がありますよね。 それも踏まえて私が大切だと思うのは、クリフトンストレングス®の診断結果を絶対的なものとして捉えるのではなく、診断結果をトリガーとして自分を見つめ自己理解を深めていくことが肝要だということです。 クリフトンストレングス®はあくまでツールに過ぎないのでどう使うかが大事です。 端的に言えば「クリフトンストレングス®は人を幸せにするためのツールであるはずなのでそういう使い方をしましょう」というのが私の一番言いたいことです。 私の場合で言うと今使っている診断結果は二回目のものです。 それはなぜか? 二回目の並び順が気に入っているからです。 もちろん自分をよく表しているのは大前提です。 一回目と二回目を比較すると、自分自身がコーチングを学びより良い生き方へと自分を変えてきた変遷が見てとれる気がするのです。 もちろんこれはあくまで私の場合であり、何回も診断を受け直す必要があるということではなく、一回目で出た資質の並びで象徴される自分を認め、受け入れ、尊重していくことが最も望ましいことかもしれません。 私の場合をもう少し補足すると、実は一回目でTOP5にいた「分析思考」が二回目の結果では17番目に下がってしまいました。 恐らく上述したようなことが自分にも起こっていた(たしかに自分の理屈っぽさを否定的に見ていた)のだと思います。 それでもどう考えても「分析思考」は上位にいるので、クリフトンストレングス®の結果としてみたら上位ではなくとも自分の感覚としてはTOP5のつもりで強みとして使う意識を持っています。 また別の意味では二回目の結果で「適応性」が上位に入ったとき、当初それが自分の才能であることにピンと来ていませんでした。 しかしながらあることをきっかけに「適応性」が確かに自分の才能としてあることに気づけてから「適応性」が自分の中ではある意味“お守り”として機能するようになりました。 「『適応性』が上位なんだから大丈夫」的に。 言いたいのは、繰り返しますがクリフトンストレングス®は人を幸せにするためにあるものであり、そういう使い方をしてナンボだということです。 端的に言えば、いかに自分の“都合よく”使うかなのだと思っています。 ご質問の意図からはだいぶずれてしまいましたがお役に立てれば幸いです。
ストレングスファインダー®徹底活用ガイド
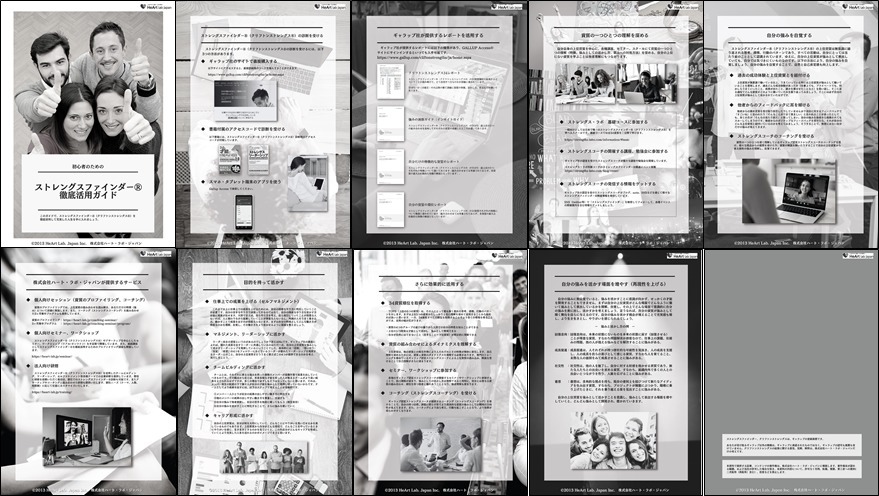 簡単なアンケート(選択式)にお答えいただき、メールアドレスをご登録いただくと上のストレングスファインダー®徹底活用ガイドをプレゼントいたします。お申し込みは、上の画像をクリックしてください。
簡単なアンケート(選択式)にお答えいただき、メールアドレスをご登録いただくと上のストレングスファインダー®徹底活用ガイドをプレゼントいたします。お申し込みは、上の画像をクリックしてください。
無料メルマガ「才能を活かして自分らしく楽に生きる方法」
思考を緩め、人間関係を改善し、自分らしく楽に生きる方法を、ほぼ毎日お届けしています。
メルマガ読者限定の特典も提供しています!