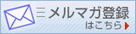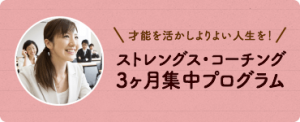「適応性」は、受け入れる
「適応性」は人間関係構築力の資質であり、原語は Adaptability です。 原語の翻訳は、文字通り“適応性”とか“順応性”とかになります。 ここで言う“適応、順応”とは、今今の状況に合わせて柔軟に適応していくとの意味合いになります。 「適応性」上位の人のありがちなセルフトークは「仕方ない」です。 何が起こったにしても「起こってしまったことは仕方ない」と、受け入れてしまえるのが「適応性」という資質です。 そういう特性から「適応性」上位の人は、不測の事態が起こっても過度に慌てることがありません。 もちろん内心は動揺しているとは思いますが、一方でジタバタしたところで状況は変わらないので受け入れた上で対応するしかないとの感覚なのです。 私自身も5番目にある資質ですが、この資質に助けられたのが5年前の熊本地震の時でした。 地震により電気、水道が止まり、いきなり不便な生活を強いられることとなりましたがそれをまさに「仕方ない」と受け入れて「今できることをやろう」と切り替えられました。 何が起こったとしてもその状況に抗わずに受け入れ柔軟に適応していく。 これが「適応性」という資質です。「適応性」は、イマココを生きる
「適応性」という資質は、まさに“イマココ”を体現している資質と言えると思います。 「適応性」上位の人が見ているのは、常に“今”です。 時間軸に対するウインドウの幅が狭いイメージです。 過去にもこだわらずすぐに忘れてしまうし、先の未来を「こうなる」「こうする」と固定化して考えることもありません。 特に未来に対する感覚は「その時点になってみないとわからない」というもの。 すなわち、未来はいくらでも変わり得るというのがそもそもの前提としてあるのです。 だからこそ、どんなことが起こっても(予定通りいかなくとも)それを受け入れられるということ。 そこからのつながりでどんな特徴が出がちかと言うと、「適応性」上位の人はあまり先の予定を入れたがらないと思います。 なぜならば、先の予定を固定化してしまうとその時何かあったとき柔軟な対応が出来なくなってしまう感覚に陥るから。 まさに私自身がそうですが、二ヶ月“も”先の予定はよっぽどのことが無い限り自ら入れることはありません。 その代わり直近で何かを依頼された場合は割と対応できることが多く、結果的に直前になってバンバン予定が埋まっていく感じなのです。 ここは自分でも最近気づいたことです。 いずれにしても「適応性」が大事にしているのは今この瞬間に適応すること。 イマココを生きるのが「適応性」という資質です。「適応性」は、目標にときめかない
「適応性」の特徴は未来を固定化して考えないことです。 言い換えると、未来はどんなふうにでも変わり得ると思っています。 だからこそ、実際に予期しないような出来事が起こったとしてもそこに抗うことなく受け入れることが出来ます。 一方、その特性が妨げとなり起こることは、目標を設定することにあまり意味を見出せなくなってしまうことです。 一年後に「〇〇を実現したい」との目標を立てたとして「一年後なんてどんな状況になっているかわからない」との感覚に襲われてしまうのです。 私はそれを「適応性」上位の人は“目標にときめかない”と表現しています。 なので、「適応性」上位の人は一般的に目標を立てそこに向かって計画的に物事を進めるのは苦手です。 裏返せば今今に反応的に動いてしまうだけに、ある意味行き当たりばったりになってしまうのが「適応性」上位の人の特徴です。 私の場合は、それに加えて「調和性」が上位の分「戦略性」が下位であり、先に何らかの狙いを置いて今を考えることも苦手です。 なのでいつでもちょー行き当たりばったり。 ここはもう諦めるしかないなぁとの境地です。 とは言えビジネスの場面において目標設定や計画性というのはある意味スキルとして求められることも多いと思います。 なので、そういうものを求められる環境にいる場合は、それが苦手な前提で工夫をするしかないと思います。 「適応性」の場合は、たとえ目標を立てたとしてもそこへの意識は時間の経過とともに必ず薄れていきます。 なので、それを前提として日々の仕事の中でそこに意識が向くように仕掛けや仕組みを作っておくことが大事だと思います。 たとえば定期的に上司との面談を設定し、今やっていることと目標のすり合わせをしていくとかです。 「目標志向」上位の人は目標から遡って日々やるべきことを考え計画に落とし込みます。 一方「適応性」の場合は日々の積み重ねが結果的にどこかに着地する感じになります。 なので、結果論であっても目標に向かっていさえすれば良いと開き直るのが得策だと思います。 そして、「適応性」の場合は外部からの刺激に反応していく感じなので、今と目標のすり合わせも内発的動機づけでやるのはなかなか難しいと思います。 だからこそ他者からの働きかけがある状態での仕組みを考えるのが効果的だと思います。 自分で書きながらなかなか難儀だなぁと思いましたが、どうしても目標に向かう計画性を要求される環境にいるのであればそういう工夫も必要だと思います。「適応性」は、飽きる
これまで書いてきたように「適応性」が大事にしているのは今今起こることに適応していくことです。 別の表現をすると、今今起こることに反応してしまうということでもあります。 それゆえに一つのことに集中して取り組むのは苦手です。 ある意味、外部からのノイズに弱い感じ。 私の場合で言えば、ブログを書いている途中でメッセンジャーでメッセージが飛んでくると、たとえ一つの文章を書いている途中であってもそっちに反応してしまいます。 その結果「あれ、どこまで書いたっけ??」となることもよくあります。 たとえて言えば四方八方から飛んでくるボールを片っ端から打ち返すような感じです。 そういう即時的な反応ができるのが「適応性」の良さでもありますが、特にノイズの多い環境において集中力の続く時間が短いのも「適応性」の特徴です。 ちょっとニュアンスは違うかもしれないですが、飽きっぽいと言っても良いかもしれません。 そして、ここもやっぱりそうなってしまうのは“仕方ない”のです。 なので、ここはそれを逆手に取って工夫をするしかないなぁと思っています。 私はよく“つまみ食い方式”と言っていますが、一つひとつの案件を出来るだけ小さなタスクに分割し一つのタスクを片づけたら次に移るというのを繰り返すのです。 こうすれば、割とうまくいくことが多いです。 私の場合は「アレンジ」も併せて上位なのでよりそのやり方が適しているのかもしれません。 後は、極力ノイズの少ない環境に身を置くというのも大事かなぁと思います。 私がよくカフェで仕事をするのもそのための工夫の一つでもあります。 自宅にいるといろんなことが出来てしまうだけに集中が続きづらいのです。 何かしら得意なことがあればその裏返しの苦手なことが必ずあります。 逆に言えば苦手を克服しようとすればその裏返しの得意を消すことにもなります。 だからその方向に行くのはお勧めしないし、あまり意味のないことだと思います。 苦手は苦手なりに逆にその特性を活かしてどう対応していくか。 それもストレングスファインダーを活用する一つの方向性です。「適応性」は、目の前にいる人に集中する
「適応性」が人間関係構築力である意味を考えてみたいと思います。 「適応性」が大事にしているのは“今この瞬間”です。 従いそれが人に向いた時は、今目の前にいる人に意識が集中することを意味します。 逆に言えば、過去がどうだったか、未来にどうつながるかは置いておいて、今目の前にいる人に合わせて対応していきます。 私自身がまさにそうですね。 「最上志向」と相まって今関わっている人に全力を尽くす。 そんな感じです。 一方、過去がどんどん流れていってしまうので、再び同じ人が目の前に現れた時以前その人にどんな対応をしたのかは覚えていないことが多いです。 だから良くあるのが 「以前知識さんに〇〇〇〇と言われたのがとても響きました」 と言われて、 「えっ、そんなこと言ったっけ?」 「ほぉー、俺っていいこと言ってるじゃん!」 的な状態になること(笑)。 いずれにしても今の状況で今目の前にいる人に100%意識を向けられるのが「適応性」の特徴です。 そしてもう一つは、相手に合わせる柔軟さの部分だと思います。 「適応性」は、飛んできたボールを飛んできたなりに受け取り、投げ返します。 それは、物事に対してだけでなく、人に対しても働いていると思います。 なので、恐らく「適応性」上位の人は、人に対する好き嫌いはあってもそこそこの付き合いが出来るという意味で大きな苦手意識は持たないのではないかと思います。 そういうところも「適応性」の人間関係構築力としての側面だと思っています。「適応性」は、漂う
「適応性」は、今を生きる資質です。 今ココにあるものを大切にする資質です。 過去に囚われず、未来を先取りせず、川の流れに身を任せるがごとく漂いながら生きています。 流れが緩やかであればただただ身を任せ、急な流れに差し掛かれば手足をバタバタさせもがきながらも切り抜けます。 すべてにおいて起こったことに起こったなりに対応していきます。 どんなことが起こってもその変化に抗わず柔軟に対応していけるのが「適応性」の強みです。 決して能動的な動きを取る資質ではないし、その意味でそれを強みとして捉えている人は少ないかもしれません。 むしろ行き当たりばったりな自分を否定的に見ている人も多くいるのではないかと思います。 私自身もかつてはそうでしたが、あることをきっかけに「適応性」は自分の最も特徴的な強みであることに気づくことができました。 https://heart-lab.jp/blog/140/ そして、その後の感覚が大事なのですが、私の場合はそのどんなことがあっても柔軟に対応できるとの強みが自分にあることを知り「適応性」をお守り代わりとして使うようになりました。 すなわち、「何かあればあったで『適応性』が何とかしてくれる」と思えるようになったのです。 もちろんそこには何の根拠もありません。 それまでと何かが変わった訳でもありません。 それでもそう思えるだけで自分の行動は大きく変わりました。 行き当たりばったりな自分から、何があっても柔軟に切り抜けられる自分へと認識が大きく変わることで、恐れずに踏み出す勇気を得ました。 そして、今ではすっかり自分のトレードマークになった感すらあります。 ということで、「適応性」上位の人に言いたいのは、これからも迷わず流れに身を任せて漂いながら生きていきましょう!ということです。 そして自分に貼り付けたレッテルを、行き当たりばったりな自分から“行き当たりばっちり”な自分へと書き換えましょう!
ストレングスファインダーの活かし方~ストレングスファインダーの基礎~
ストレングスファインダー®で自分の“トリセツ”を作りませんか?
(サンプルは、下の画像をクリックしてください)。
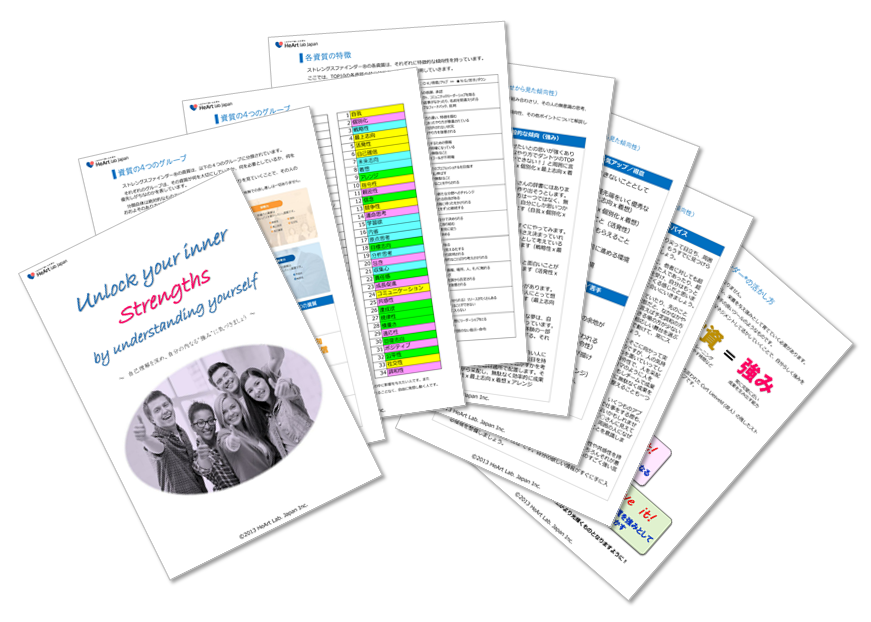 口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。
詳細、お申し込みは、こちら から。
口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。
詳細、お申し込みは、こちら から。
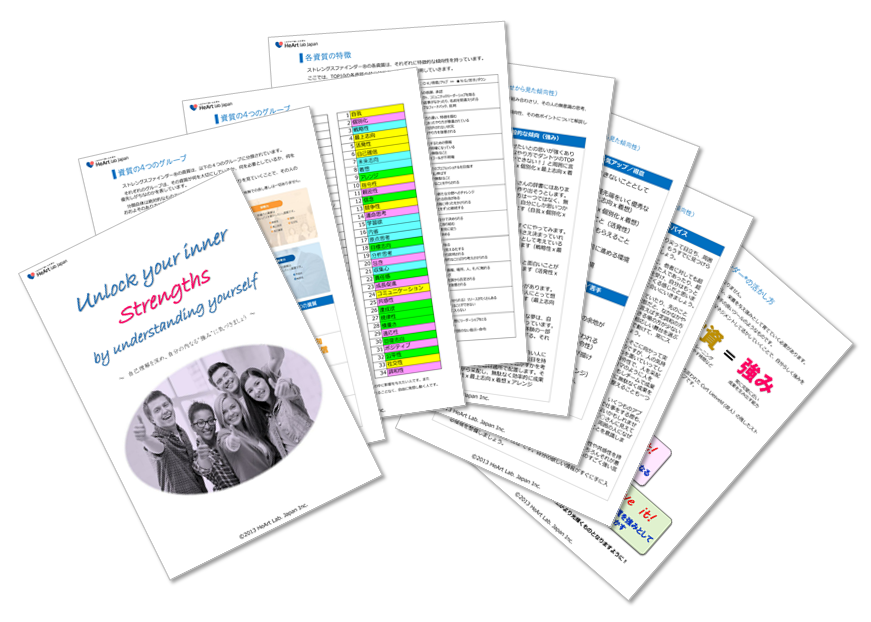 口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。
詳細、お申し込みは、こちら から。
口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。
詳細、お申し込みは、こちら から。
無料メルマガ「才能を活かして自分らしく楽に生きる方法」
思考を緩め、人間関係を改善し、自分らしく楽に生きる方法を、ほぼ毎日お届けしています。
メルマガ読者限定の特典も提供しています!